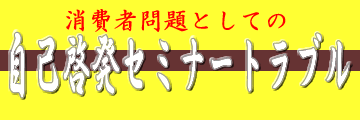
自己啓発セミナー契約・勧誘トラブル |
||
| Since 2005/08/12 | 更新:2006/5/21(履歴) | 作成:mamma |
当サイトの趣旨
自己啓発セミナーの定義
主なトラブル
├未成年者契約
├ブラインド勧誘
├不実の告知
├威迫・困惑
├不退去
├クーリングオフ妨害
└その他
セミナー勧誘は訪問販売
セミナーに勧誘されたら
知っておきたい法律
├未成年者取消(民法)
├消費者契約法
├特定商取引法
│├施行規則
│└施行令
└東京都消費生活条例
└施行規則
契約解除・取消をする為に
自己啓発セミナー会議室
リンク
運営者紹介
ブログ
免責事項
●不実の告知・断定的判断の提供
普段、生活をしていて「約束」というものをする事がよくあると思います。
・飲み会の約束
・何らかのモノを貰ったり貸してもらう約束
・一緒に遊びに行く約束
・etc
その約束をする上で、当たり前のように守られているのが「約束をする上で嘘をつかない」という事ですね。
例えば、あなたに気になる異性(仮にAさんとします)がいたとしましょう。そのAさんとあなたの共通の友人(Bさん)から遊びの誘いを受けました。聞けば気になるAさんも来るとの事。仕事が忙しくてなかなか時間が作れないのですが、Aさんが来るならと、無理矢理時間を作って遊びに行く事にしました。
ところが、遊びに行った先にはAさんはいません。遅れて来るのかと思ったのですがそうでもないようです。そこで、BさんにAさんはどうしたのか聞いてみました。すると、驚く事にAさんが来る予定などはじめから無くて、あなたを呼び出す為に「Aさんが来る」と言ったというのです。つまり、「Aさんが来る」という嘘をつかれて遊びに行くという約束をさせられたわけです。
「遊びに行く」という約束をする為に重要な判断材料になったのは「Aさんが来る」という事です。Aさんが来ないのなら、仕事が忙しいので約束はしなかったでしょう。
このような事を法律では「不実の告知」と言います。契約を結ぶ為に重要な判断材料になる事柄に対して不実(嘘)を告知(伝える)事です。
また、先程の例えで、Bさんから「今日来ればAさんと交際できる」と言われていて、それが約束をする上で重要な判断材料となる場合を考えて見ましょう。
「そんな事、簡単に信じるヤツはいない」なんて思うかもしれませんが、あくまで例えなので大目にみてください。
この場合は、断定的判断の提供と言い、契約を結ぶ為に重要な判断材料になる事柄で不確実な事を確実であるように伝える事です。
○ケース1
山田さんは、友人の田中さんに田中さんが現在受講している自己啓発セミナーに誘われました。興味はあるのですが、受講料も高いし内容も良く分からないので今一、受講してみようという気持ちになれません。
田「どうだ?やってみないか?」
山「う〜ん・・・。興味はあるんだけどな・・・」
田「これを受講すればお前も絶対に変われるって。俺を見てみろよ」
山「そうだな、お前、なんか前よりも明るくなって前向きになってるよな」
田「だろ?お前もセミナー受ければそうなるぜ」
山「そうか、やってみようかな。でも、セミナーって勧誘とかしなくちゃいけないんだろ?」
田「そんな事ないよ」
山「だって、今、お前は俺を勧誘してるじゃないか」
田「いや、俺は自主的にお前にセミナーを紹介してるだけでさ、別に強制されてやってるわけじゃないんだ」
山「そうなのか。じゃあ、俺もそのセミナー受けてみるよ」
山田さんは、セミナーを受講する事に決め契約書にサインをしました。
さて、セミナーを受講した山田さん、なんだか思っていたのと様子が違う事に気付き始めました。明るくなって前向きになるどころか、受講生同士で罵倒しあったりトレーナーやスタッフからきつい事を言われまくって、どんどん落ち込んでいきます。それでも、向上心があるので、懸命にセミナーを受け、ついに第3段階まで進みました。
そこで待っていたのは、「セミナーを周りの人たちに紹介する」という名目の勧誘実習です。個人個人に「目標」という名前のノルマが与えられます。ここで、遂に最初に田中さんに言われた事と違う事に完全に気付いたのです。
このケースでは、1つの不実の告知と1つの断定的判断の提供が行われています。
勧誘の強制は無いと言っていたにもかかわらず、実際は勧誘実習がありました。(不実の告知)
明るくなれる・前向きになる、というような個人差がある事を確実に得られるように言っています。(断定的判断の提供)
これらの行為は「特定商取引に関する法律(特商法)」と「消費者契約法(消契法)で禁じられています。自己啓発セミナーは組織的に、このような事をやるのを推奨しています。しかし、セミナー会社にクレームが行った場合、「受講生の判断で行ったことであり受講生の責任である」と責任を回避しています。
■消費者契約法
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
■特定商取引に関する法律
第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。